
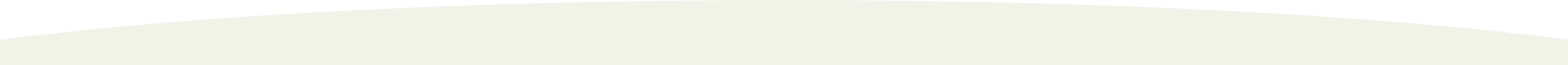


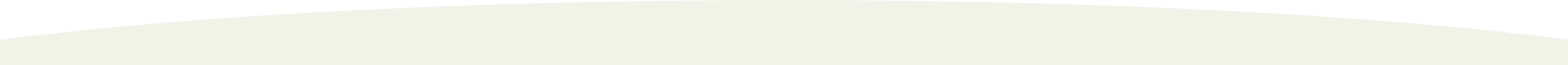

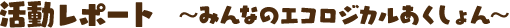
盈進中学高等学校環境科学研究部 (広島県)
久しぶりに因島で魚類調査を行った。干潟・感潮域・中流域・中上流域の4カ所で調べてみた。後から記録を見て分かったのだが、広島県で僕たちが初めてヒナハゼを見つけたのが2年前の11月17日である。昨年の秋は、調査をしていない。行く途中で意見が分かれた。亜熱帯性の両側回遊魚だから「水温の下がる寒い冬をのりきれるはずがない。死滅回遊にたまたま出くわしたのだ。」というのと「近辺に温排水や伏流水の湧く暖かい水域があるとすれば、繁殖できる。今回採集できる。」というものである。


干潟では、一昨年に加えヒモハゼが見つかった。小さな島にしてはテッポウエビ類の巣穴も多く、この干潟はとても多様性が豊かだった。
感潮域では、一昨年生息していた地点ではヒナハゼは見つからず(いれば簡単に採れる)、近場のポイントを探ってみた。いた! 一度見つけると次々に採れる。ほどほどで他の魚種の採取を行った。
中流域では、巨大なシマヨシノボリやウナギにまじって、オオクチバスやメダカなどが採取できた。
1.ヒナハゼはほぼ定着していると思われた。しかも一昨年より個体数も増えている。もともと熱帯性の両側回遊魚のため、海水温の上昇で分布を拡大しているとされているが、瀬戸内海でも同様のことが起きていると感じた。
2.この島の川は、過去に何度か枯れていると分かった。本来生息するはずの純淡水魚がいないからである。
3.特定外来種のカダヤシ・オオクチバス・ブルーギルは、純淡水魚だが、外国産で、いずれも蚊の駆除や上流のダムでの釣りのため、人の手によって放流されたものである。
4.唯一生息してもおかしくないメダカも、写真のように白く変異したものや緋色のものが含まれていた。自然分布とは到底思えない。
5.他に採取できた魚たちを写真記録しておき、部員たちと学習会をしていった。
地球温暖化の議論はよく聞くけれど、普段の生活ではなかなかぴんとこない。でも、実際に自然とふれあってみると確実に進んでいることを肌で感じる。フィールドは大切ですね。




 用水路で釣り調査
用水路で釣り調査
盈進中学高等学校環境科学研究部(広島県)
 17種の淡水魚を確認!広島県福山市 芦田川支流
17種の淡水魚を確認!広島県福山市 芦田川支流
盈進中学高等学校環境科学研究部(広島県)
 久しぶりの芦田川淡水魚調査
久しぶりの芦田川淡水魚調査
盈進中学高等学校環境科学研究部(広島県)
 ザリガニ退治できず、みお筋づくりに励む
ザリガニ退治できず、みお筋づくりに励む
盈進中学高等学校環境科学研究部(広島県)